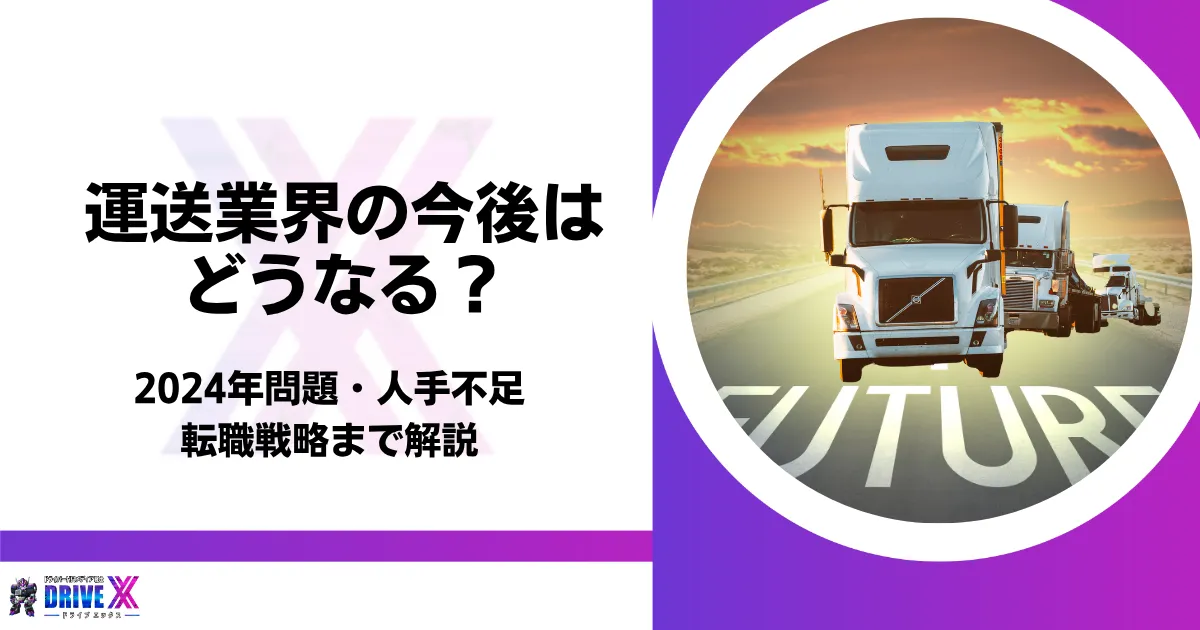運送業界で働いている方や転職を検討している方の中には、「このまま運送業界で働き続けても大丈夫なのか」「今後ドライバーになっても将来性はあるのか」と不安に感じている方も多いでしょう。
2024年問題や人手不足といった課題が注目される一方で、EC市場の拡大により物流需要は継続的に増加しており、運送業界は社会インフラとして欠かせない存在です。
この記事では、運送業界の今後の動向と将来性、2024年問題の影響、そして転職を成功させるためのポイントを詳しく解説します。
最新のデータを基に、運送業界での転職やキャリアアップを検討している方に向けて、具体的で実践的な情報をお届けします。
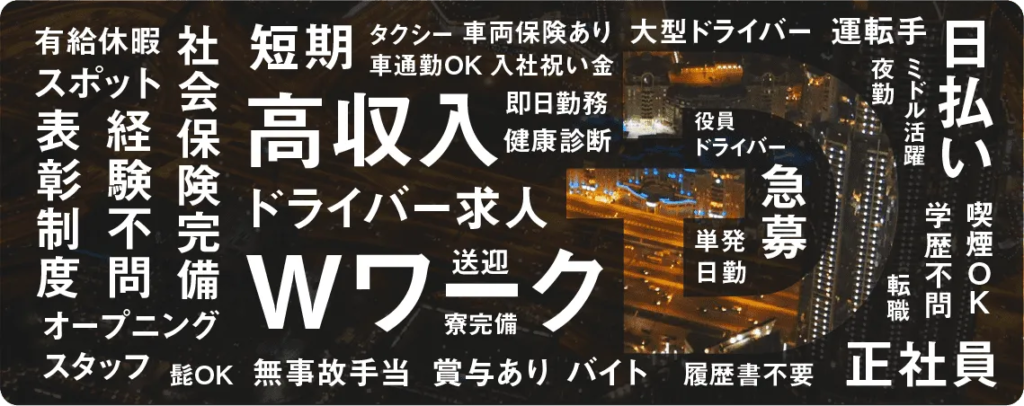
- 貨物・送迎・配送など多種多様なドライバー求人情報
- 地域×給与×雇用形態など希望条件で選べる
- 掲載数2,000件以上
ドライバー・運転手・配送の求人情報をお探しの方は「DRIVE X」へ!
貨物・送迎等の多彩な求人情報をはじめ、地域や雇用形態など、
あなたの希望に合った求人情報をお届けします!
\ 掲載数2,000件以上 /
運送業界の今後はどうなる?将来予測と業界動向

ネット通販の普及や消費行動の変化により、運送業界はかつてないほど注目を集めています。一方で、ドライバー不足や2024年問題など、深刻な課題も浮き彫りになっています。
ここでは、最新のデータや業界動向をもとに、運送業界の今後の予測について解説します。
物流需要は増加傾向
EC市場の拡大により宅配便取扱個数は年々増加傾向にあり、物流需要は継続的に高まっています。令和5年度の宅配便取扱個数は50億733万個となり、前年度と比較して145万個・約0.3%の増加となりました。
※出典:国土交通省「令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について」
運送業界は社会インフラとして必要不可欠な存在であり、モノがある限り運送業界がなくなる可能性は極めて低いです。
技術革新による業界の変化
近年、運送業界ではデジタル技術の活用が急速に進んでおり、業務の効率化や生産性の向上が図られています。たとえば、配車管理システムやデジタルタコグラフの導入により、運行状況の可視化や効率的なルート管理が可能になりました。
また、AIを活用した配送ルートの最適化や車両の予防保全技術も実用段階に入りつつあり、より安定した物流体制の構築が期待されている状況です。
さらに、電気自動車(EV)やドローン配送などの新技術が導入され始めており、環境負荷の低減と同時に新たなビジネスモデルの創出にもつながっています。
このように運送業界では業務の効率化と人手不足への対応が進んでおり、この流れは今後も継続すると考えられます。
運送業界が抱える構造的課題
慢性的なドライバー不足と高齢化により人材確保が困難な状況が続いています。有効求人倍率は他業界と比較して高い水準を維持しており、人材確保の難しさを示しています。
さらに、燃料費の高騰や人件費の上昇といったコスト増加も、収益を圧迫する要因です。適正な運賃を確保できない企業では、安定した経営の継続が難しくなるおそれがあります。
また、2024年問題の影響も見過ごせません。時間外労働の上限規制により、輸送力の低下が懸念されており、業界全体での対応が求められています。
運送業界の今後を左右する2024年問題と法規制の影響
2024年4月からトラックドライバーの時間外労働960時間上限規制が適用され、運送業界に大きな変化をもたらしています。
全日本トラック協会の資料を基に、2024年問題の具体的な影響と対策について解説します。
2024年問題の現状と今後への影響
2024年4月からトラックドライバーの時間外労働960時間上限規制が適用開始されました。この規制により、これまで長時間労働に依存していた運送業界では大きな変化が求められています。
国の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」では、2024年に14.2%、2030年には34.1%の輸送能力不足が予測されています。
※出典:経済産業省「持続可能な物流の実現に向けた検討会」
輸送力の低下が続けば、商品の流通が滞り、企業活動だけでなく消費者の暮らしにも影響を及ぼします。今後は、より効率的で持続可能な物流の仕組みづくりが必要です。
トラックドライバー不足の深刻化予測と人材確保の課題
運送業界では既に深刻な人材不足が続いており、有効求人倍率が他業界と比較して高い水準を維持しています。この傾向は年々悪化しており、人材確保が運送業界全体の課題です。
特に問題となっているのが、ドライバーの平均年齢の上昇です。現在の運送業界では50代以上の割合が高く、若年層の新規参入が極めて少ない状況が続いています。
このような構造的な問題に対し、業界では女性ドライバーの積極的な採用や労働環境の改善など、新たな人材確保策を模索しています。しかし、これらの取り組みだけでは根本的な解決には至らず、業界全体での継続的な努力が求められているのが現状です。
働き方改革が運送業界の今後に与える長期的変化
働き方改革の一環として、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。これにより、従来は対象外だった中小企業にも大企業と同じ水準の規制が適用され、人件費の負担が大きくなっています。
こうした背景から、多くの運送会社ではDX(デジタルトランスフォーメーション)による業務の効率化が求められています。従来の人の手に頼った管理体制では、増加するコストや規制への対応が難しい状況です。
また、「同一労働同一賃金」の原則も進み、正規・非正規社員の待遇格差の是正が求められています。これに伴い、各企業では雇用制度の見直しが進み、職場の公平性を重視する動きが強まっています。
今後の運送業界では、働きやすい環境づくりと生産性向上の両立が必要です。単なる規制対応にとどまらず、長期的に安定した経営を目指さなくてはいけません。
運送業界の今後の課題解決に向けた対策
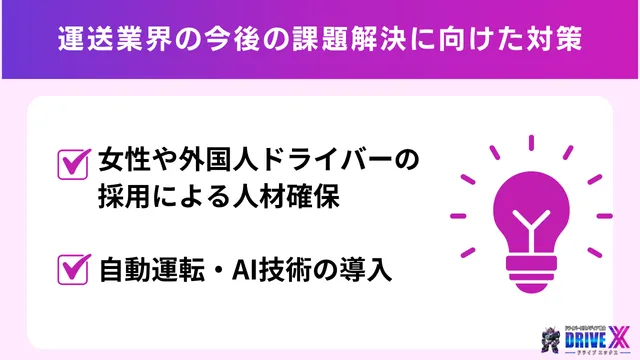
2024年問題や人手不足といった深刻な課題を受け、運送業界ではさまざまな対策が講じられています。
人材確保に向けた取り組みに加え、先進技術の導入も進み、業界全体で変革の動きが広がっています。
ここでは、運送業界の課題解決に向けた具体的な取り組みについて見ていきましょう。
業界全体で進む人材確保・育成戦略
2024年頃からは、女性や外国人ドライバーの採用が本格化しています。これまで男性中心だった業界において、多様な人材の受け入れが進んでいます。
同年には「特定技能・自動車運送業」が創設され、外国人のドライバー雇用が可能になりました。これも人手不足の解消に向けた新たな選択肢の一つです。
他にも各社で運転免許の取得支援や研修制度の充実といった育成環境の整備も進んでおり、未経験者でも安心して働ける仕組みづくりが重要視されています。
さらに、労働環境の改善によって離職率の低下や定着率の向上が見られ、働きやすい職場づくりが人材確保の柱となりつつあります。
自動運転・AI技術導入の現実と今後の展望
運送業界では、AIを活用した業務の効率化が加速しています。たとえば、配送ルートの最適化や需要予測システムの導入が進み、現場の負担軽減と生産性の向上が期待されています。
こうした技術革新の流れの中で、注目を集めているのがドローン配送です。2025年の実用化を目指して各地で実証実験が行われており、大手企業も積極的に参入しています。
また、自動運転技術についても進展が見られます。現在は実証段階ですが、将来的には人手不足の緩和策としての役割が期待されています。
今後もこうした技術導入は、業界全体の持続可能性を支える重要な要素となっていくでしょう。
今後の運送業界で生き残る企業の特徴
運送業界の変化に対応し、持続的な成長を実現する企業には以下の特徴があります。
- IT導入実績があり、公式サイトでDX推進を明記している企業
- 大型免許保有者の割合が高く専門性の高いサービスを提供している企業
- 求人票で研修や資格取得支援制度を明示している企業
2024年問題による労働時間制限への対応策として、IT技術への投資は今や不可欠です。デジタル技術を活用した業務効率化により、限られた人員・時間で成果を出せる企業ほど、今後も競争力を維持できると考えられます。
同様に、特殊車両や危険物輸送といった高い専門性を持つ企業も、価格競争に巻き込まれにくく、安定した収益を確保しやすい点で有利です。
さらに、人材育成に積極的な企業は従業員満足度が高く、長期的な雇用安定につながるため転職先として安心感があります。
今後の運送業界で倒産リスクがある企業の特徴
一方で、運送業界には経営が不安定で倒産リスクの高い以下の特徴を持つ企業も存在します。
- 資本金1千万円未満の小規模零細企業
- 慢性的な人手不足で常に求人を出している企業
- 労働条件が曖昧で、求人の基本給と諸手当の内訳が不明確な企業
小規模零細企業は経営に余裕がない可能性が高く、大手よりも倒産リスクが高いです。実際に2023年のデータでは、資本金1千万円未満の企業が運送業界の倒産全体の約7割※を占めています。
また、頻繁な求人募集は離職率の高さを示唆し、労働条件の曖昧さは適正な給与支払いへの不安を表しています。
転職を検討する際は、企業の公式サイトや求人内容を詳細に確認し、安定した経営基盤を持つ企業を選択することが重要です。
※出典:東京商工リサーチ「2023年の運送業の倒産 過去10年で最多の328件」
今後の運送業界で働くためのドライバーキャリア戦略
運送業界の変化に対応し、安定したキャリアを築くためには戦略的な取り組みが必要です。
将来性のある職種選択と効果的な転職戦略について詳しく解説します。
将来性のある運送職種と必要スキル
大型・けん引免許を活用した長距離トラック運転手は、高い専門性と技術力が求められる職種として将来性があります。大型免許保有者は市場価値が高く、高収入を目指したい方にもおすすめです。
さらに、危険物取扱者などの資格を取得することで、タンクローリーなど特殊車両による輸送業務にも従事できるようになります。また、運行管理者の資格を取得すれば、ドライバーから内勤職へのキャリア転換も可能であり、将来的な選択肢も広げられます。
人手不足が進む運送業界では、即戦力となる運転技術と安全意識の高い人材が特に重宝されます。将来を見越して、今のうちから運送業界に必要な免許や資格を取得しておくことをおすすめします。
年収アップを実現する転職戦略
年収アップを実現する方法は資格取得だけではありません。大手運送会社への転職も一つの手段です。
大手運送会社の中には、700万円を超える年収を実現するケースもあり、転職者にとって多くのチャンスが広がっています。福利厚生の充実度も企業規模に比例する傾向があります。
また、深夜勤務や長距離運送への転向により、収入の増加を目指すことも可能です。
今後に期待できる運送企業を探すならドライブエックスの求人をチェック!
運送業界での転職を成功させるためには、将来性があり、安心して働ける企業を見つけることが大切です。
ドライブエックスでは、安定した経営基盤を持つ企業や、長く働ける職場環境が整った求人情報を多数掲載しています。
なかには、大型免許や運行管理者などの資格取得を支援する制度を設けている企業もあり、キャリアアップを目指す方にもおすすめです。
将来を見越して運送業界への転職を考えている方は、ぜひ一度ドライブエックスの求人をチェックしてみてください。
\ 豊富な職種で希望が叶う! /
運送業界の今後に関するよくある質問
運送業界は本当になくなる?
運送業界がなくなることはありません。EC市場の拡大により宅配便取扱個数は継続的に増加しており、令和5年度は50億733万個と前年度比0.3%の増加を記録しています。
運送は社会インフラとして必要不可欠な存在です。技術革新により業務効率化は進みますが、モノがある限り運送業界の需要は継続します。
今から運送業界に転職しても大丈夫?
人手不足が深刻化している現在、運送業界への転職は有利な状況です。有効求人倍率が高く、未経験者でも採用される可能性があります。
運送業はきついイメージを抱く方も多いですが、2024年問題により労働環境の改善が進んでおり、以前よりも働きやすい環境が整備されています。興味がある方は、一度求人をチェックしてみましょう。
\ 豊富な職種で希望が叶う! /
今後トラックドライバーはどのくらい不足する?
全日本トラック協会の試算によると、2024年に14.2%、2030年には34.1%の輸送能力不足が予測されています。これは営業用トラックの輸送能力での計算です。
※出典:経済産業省「持続可能な物流の実現に向けた検討会」
人材不足は今後も継続する見込みであり、ドライバーの需要は高い水準を維持すると予想されます。この状況は転職を検討している方にとって有利な市場環境といえます。
運送業界の今後を見越して最適な転職先を見つけよう
運送業界は、2024年問題や人手不足といった課題を抱えつつも、EC市場の拡大に伴って物流需要が引き続き伸びています。
近年では技術革新や労働環境の改善が進み、以前よりも働きやすい業界へと変わりつつあるのが現状です。
今後はデジタル化への対応力や専門性の高さがより重視されます。たとえば、大型免許や危険物取扱者などの資格を取得することで、自身の市場価値を高め、安定したキャリアを築くことが可能です。
人手不足が続く今は、転職を考えるうえで大きなチャンスでもあります。
運送業界で新たな一歩を踏み出したいとお考えの方は、ドライブエックスの求人情報をご覧ください。将来性のある優良企業を多数掲載しており、ご希望の条件に合う転職先を見つけられます。
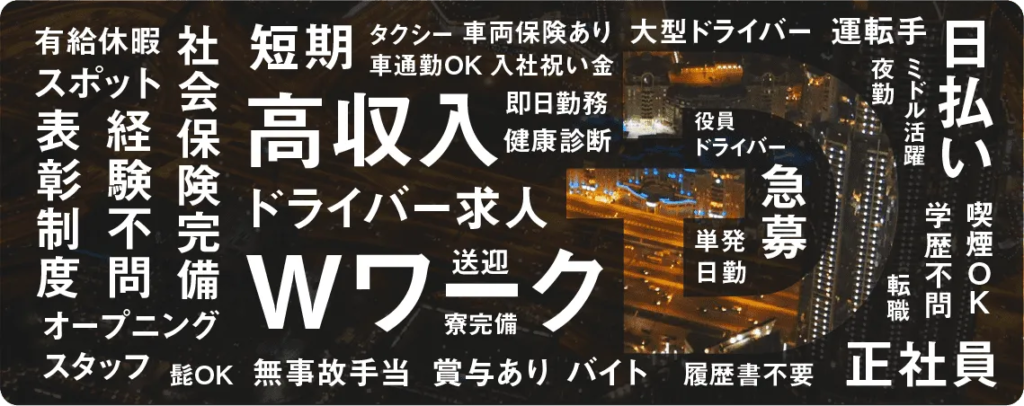
- 貨物・送迎・配送など多種多様なドライバー求人情報
- 地域×給与×雇用形態など希望条件で選べる
- 掲載数2,000件以上
ドライバー・運転手・配送の求人情報をお探しの方は「DRIVE X」へ!
貨物・送迎等の多彩な求人情報をはじめ、地域や雇用形態など、
あなたの希望に合った求人情報をお届けします!
\ 掲載数2,000件以上 /